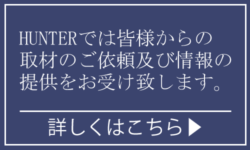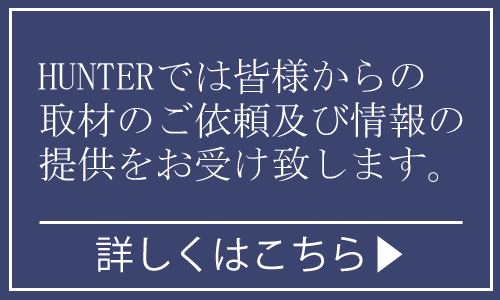新聞記者として長くアジアを担当したので、インドやパキスタン、アフガニスタンから東南アジアまで、この地域の国々はかなり頻繁に訪れた。石油をめぐる連載記事の取材で湾岸の産油国を回ったこともある。だが、「担当地域外」ということで、ヨーロッパの国々を取材する機会はほとんどなかった。
古稀を過ぎて、体力も気力も徐々に衰えてきた。「まだ余力があるうちに取材の空白域に足を運んでみたい」と思い、かねて訪ねてみたかったドイツに10日間の旅に出た。
10月上旬、空路、フランクフルトからから入り、中央駅近くのホテルにチェックインした。フランクフルトの繁華街は、中央駅の前に「こぎれいな歌舞伎町」をドスンと置いたような風情だ。駅前から延びる街路にはそれぞれ警察官が配置され、角々には中東系とアフリカ系の若者がたむろしていた。
中央駅から数ブロック奥に入っただけで、あやしいネオンが光り輝き、辻々には街娼が立っている。小さな紙片を広げてコソコソ売買しているのは麻薬だろう。大都市らしい猥雑さだ。夜遅く、散策を終えて駅前のホテルに戻ったが、明け方までパトカーのサイレンがけたたましく鳴り響き、しばしば眠りを妨げられた。
翌朝、駅前のカフェに入った。店員の会話に耳を傾けていたら、「タシャクル」という言葉が聞こえてきた。アフガニスタンの共通語ダリ語(ペルシャ語方言)で「ありがとう」の意味だ。「私は日本から来た。あなたたちはアフガンから?」と英語で尋ねると、少し驚いたような表情で「そうです」と答えた。その店員はウズベク人だという。そこで、カウンターにいるもう1人の店員に「あなたはパシュトゥン人か」と問うと、ビンゴだった。
「なんで分かる」と聞くので、私は「元ジャーナリストで、アフガニスタンには取材で何度も行ったことがある」と答えた。パシュトゥンの若者は、首都カブール北方のパンジシール渓谷の近くで生まれたという。パンジシールと聞いてすぐに思い浮かぶのは、タジク人武装勢力の指導者、マスードである。
マスードが率いる勢力は1992年に社会主義政権を倒して権力を握ったが、4年後にはパシュトゥン人主体のタリバンに首都を追われた。マスードは拠点のパンジシール渓谷に立てこもってタリバンに抵抗し続けたが、2001年9月、アルカイダのメンバーと見られる男たちに自爆テロで殺害された。
当時、アフガニスタンを支配していたタリバンとその庇護下にあったアルカイダにとって、親欧米のマスードはアメリカとの戦争を始めるにあたって「障害になる人物」と見られていた。アメリカと手を組み、背後から攻めてくる恐れがあったからだ。
オサマ・ビン・ラディン率いるアルカイダのメンバーが旅客機を乗っ取り、世界貿易センターと米国防総省に突っ込んだのは、マスード暗殺の2日後、9月11日だった。「アメリカとの聖戦(ジハード)」を始める前に、彼らは「背後の敵」を始末したのである。
パシュトゥンの若者に「ドイツに来てどのくらいになる?」と尋ねた。「20年以上。タリバン政権になって逃げてきた」という。この感じならアフガン料理の店もあるはず、と思って探したら、すぐ近くにレストラン「カブール」があった。その日の夜、この店で羊肉と細切りニンジン、レーズンの炊き込みご飯「マヒチャ・パラウ」を食べた。懐かしい味がした。

戦火のアフガニスタンから逃れる人々の流れは、1979年のソ連のアフガン侵攻とその後の内戦、1990年代のタリバン政権成立前後の混乱、そして2001年9・11テロ後のアメリカとの戦争、と絶えることなく続いた。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によれば、隣国イランとパキスタンには今なお、合わせて500万人を超えるアフガン難民がいる。
隣国での苦しい生活から何とか抜け出したいと願うアフガン難民は、より良い暮らしを求めてヨーロッパを目指す。その中で、最も多くのアフガン難民を受け入れてきたのがドイツだ。連邦統計庁のデータによると、国内のアフガン人は2022年時点で42万人を上回る。ドイツでは、帰化した外国人やドイツ生まれで国籍を取得した子どもは統計上、外国人として扱われないので、アフガン系の人口はこれよりかなり多いと見ていい。
第2次大戦後、ドイツは労働力不足を補うため、トルコやイタリア、スペインなどから大量の移民を受け入れた。彼らは「ガスト・アルバイター(ゲスト労働者)」と呼ばれ、主に鉄鋼業や鉱業、農業部門などで働き、ドイツの戦後復興とその後の経済成長を底支えした。移民・難民のいわば「第1波」で、その数はトルコ人だけで約300万人とされる。
この移民政策は1973年の石油危機で景気が後退すると打ち切られたが、母国に帰らず、家族を呼び寄せて定住する者が多かった。イタリア人やスペイン人はあまり目立たず、社会に溶け込んでいったが、イスラム教徒のトルコ人は肩を寄せ合い、ドイツの中に「別のもう一つの社会」を形成していった。
ドイツは「資格社会」である。ほとんどの職業で公的な資格が必要とされ、一定の教育と職業訓練を経て資格を取らなければ、しかるべき職業に就けない。ドイツ語を覚え、ドイツの習慣に合わせるだけでも大変だ。それを乗り越えて、こうした資格を取るのは容易なことではない。多くのトルコ人は低賃金の仕事で糊口をしのぐしかなかった。
それはドイツ国内でも欧州各国でも広く知られたことだったが、ドイツ国内の「もう一つの社会」の問題にすぎないとして、声高に議論されることはなく、内外のメディアで取り上げられることも極めて少なかった。
ドイツの憲法である基本法には「政治的迫害を受ける者は庇護権を享有する」という条文がある。ナチス時代の圧政を繰り返さないために設けられた規定だ。これがあるため、「ドイツはずっと、難民に広く門戸を開いてきた」と受けとめられがちだが、必ずしもそうではない。国際的なルールに沿って粛々と難民として受け入れてきた、というのが実情だ。国内のトルコ人問題がトゲのように刺さったままであり、慎重な姿勢を保たざるを得なかったのだろう。
それでも、「難民鎖国」と批判される日本に比べれば、はるかに多くの移民と難民を受け入れてきた。アフガン難民に限らず、戦火に追われ困窮した人たちはドイツを目指した。1991年以降、旧ユーゴスラビアでの紛争が激しくなると、押し寄せる難民は急増し、翌1992年には40万人を超える難民がドイツに流れ込んだ。移民・難民の「第2の波」である。
そのピークが過ぎ、落ち着きを取り戻した頃、今度はシリアやイラク、スーダンなど中東アフリカ諸国からものすごい数の難民が押し寄せてきた。欧州連合(EU)には「最初に難民を受け入れた国が責任をもって対処する」というルールがあった。ダブリン規約と呼ばれるもので、特定の国に難民が集中するのを防ぐために定めたものだが、大波に直面したイタリアやギリシャ、オーストリアなどからは「負担に耐えきれない」と悲鳴が上がった。「2015年欧州難民危機」である。
混乱が深まる中で動いたのがドイツだった。当時のメルケル首相はダブリン規約にこだわることなく、「すべての難民を受け入れる」と宣言した。難民政策を大転換し、門戸を大きく広げたのである。国内から湧き上がった批判を、彼女は「私たちはやり遂げる」「困っている人たちに手を差し伸べたことで謝罪しなければならないというのなら、ドイツは私の国ではない」と一蹴した。その決断は、EUの境界周辺で立ち往生する難民たちを何よりも勇気づけるものだった。2015年から翌年にかけて、ドイツには100万人近くの難民が殺到した(グラフ参照)。

中東やアフリカから押し寄せた「第3の波」。ドイツは難民支援を担当する職員や関係施設の拡充に追われ、中央政府と州政府の予算も膨らんでいった。そこへ、2022年のロシアによるウクライナ侵攻である。戦争が激しくなるにつれて、ウクライナから「第4の波」が押し寄せた。ドイツが受け入れた難民はポーランドに次いで多く、100万人を上回った。
トルコからの移住者からウクライナ難民まで、人口約8500万人のドイツは約730万人(全体の8%)の外国人を抱えるに至った。欧州諸国の難民支援は手厚い。とりわけドイツは、難民として認定した人だけでなく、難民申請中の人にも住居を提供し、当面の生活費を支給する。申請した本人だけでなく、子どもや家族向けのドイツ語習得プログラムも充実している。
当然のことながら、移民と難民を支援する予算は膨らむ一方だ。豊かとはいえ、ドイツ経済にかつての勢いはない。国内では少子高齢化と地方の過疎化が進む。「難民ではなく、私たちのために税金を使え」という声が高まるのは避けられないことだった。
16年にわたってドイツを率いたメルケル元首相は、名宰相として今でも海外では高く評価されているが、ここ数年、国内では風向きが変わってきた。「いくら何でも、ここまで難民を受け入れる必要があったのか」「プーチンとツーカーの仲と言われていたのに、ロシアのウクライナ侵攻を止められなかったではないか」といった厳しい批判にさらされている。
こうした流れの中で、今年9月にドイツで行われたチューリンゲンの州議会選挙では、反EUと反移民を唱える極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が第1党に躍り出た。ザクセン州とブランデンブルク州でも躍進し、第2党になった。反ナチスを国是としてきたドイツで極右勢力がこれほど伸びたのは戦後初めてであり、衝撃的な結果だった。
多くのメディアは「東西ドイツの統一後も旧東ドイツ地域は経済的に立ち遅れたままだ。経済格差への不満が噴き出した」と分析したが、その底流に「難民政策への不満」があったことは間違いないだろう。旧東ドイツ地域以外でも確実に支持者を増やしているからだ。
「移民と難民の第4波」が打ち寄せるドイツで、何が起きているのか。ドイツは大波に耐えられるのか。ベルリンにある極右政党AfDの本部を訪れ、彼らの声に耳を傾けてみた。次のコラムで、ドイツ政治の底流を探ってみたい。
(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)
長岡 昇(ながおか のぼる)
山形県の地域おこしNPO「ブナの森」代表。市民オンブズマン山形県会議会員。朝日新聞記者として30年余り、主にアジアを取材した。論説委員を務めた後、2009年に早期退職して山形に帰郷、民間人校長として働く。2013年から3年間、山形大学プロジェクト教授。1953年生まれ、山形県朝日町在住。
≪写真&グラフ≫
◎難民キャンプの子どもたち(著作権フリーの写真サイトPexelsから)→こちら
◎フランクフルト中央駅の近くにあるアフガン料理店「カブール」→ミュンヘナー通りとモーゼル通りの交差点近く=2024年10月10日、筆者撮影
◎ドイツへの難民申請者数の推移→ドイツ連邦移民難民庁のデータを基に作成
≪参考サイト&文献≫
◎調査報道サイト・ハンター「アフガニスタンの苦悩と誇り」→こちら
◎英語版ウィキペディア「Afghans in Germany」→こちら
◎「ドイツの『難民』問題とアフガン人の位置」(嶋田晴行、立命館国際研究2019年2月)→こちら
◎「ドイツ在住トルコ系移民の社会的統合に向けて」(石川真作、立命館言語文化研究29巻1号)→こちら
◎「ドイツの移民政策—-統合と選別」(前田直子、獨協大学大学院外国語学研究科)→こちら
◎「ドイツはなぜ難民を受け入れるのか」(難民支援協会、2016年8月26日)→こちら
◎ドイツ語版ウィキペディア「Bundesamt für Migration und Flüchtlinge」→こちら
◎『移民・難民・外国人労働者と多文化共生―日本とドイツ/歴史と現状―』→増谷英樹編、有志舎







-150x112.jpg)