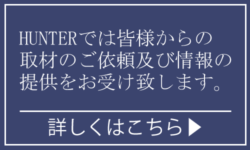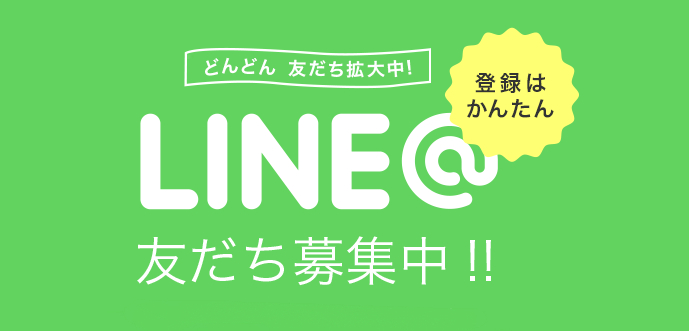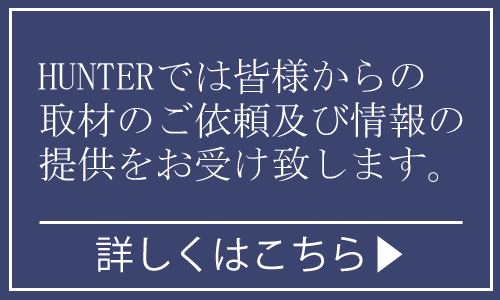【速報】江差看護学院パワハラ裁判で道が仰天主張|第三者調査を全否定「ハラスメントなかった」
- 2024/12/25
- 社会
- パワハラ, 北海道立江差高等看護学院, 第三者調査委員会, 自殺
北海道立江差高等看護学院で教員のパワーハラスメントを苦に在学生が自殺した問題で、遺族が起こした裁判の被告となった北海道(鈴木直道知事)がパワハラの事実を全否定し始めたことがわかった。複数のハラスメントを認定した道の第三者調査には問題があったとし、認定事案の全件についてパワハラとは認められないとの主張。知事や担当課の謝罪をも否定しかねない主張に、遺族側は大きなショックを受けている。

■謝罪後一転、パワハラ否定
裁判は、江差看護学院の学生だった長男(当時22)を2019年に亡くした女性(48)が本年9月に提起。のちの第三者調査で認定されたパワハラ被害への適切な賠償を求めるもので、提訴翌月の10月下旬に函館地方裁判所(五十嵐浩介裁判長)で最初の口頭弁論を迎えたところだった(既報 )。
本サイトなど既報の通り、江差では複数の教員による学生への長期間にわたるパワーハラスメントが指摘され、21年に設置された第三者調査委員会が少なくとも11人の教員が計53件のパワハラに関与していた事実を認めた。裁判になっている男子学生の事案はこの53件に含まれていなかったが、22年になって遺族が道へ調査を求めたことで新たな第三者委が発足、23年までにまとめられた調査書で自殺とパワーハラスメントとの相当因果関係が認められ、道が遺族へ直接謝罪するに到った。その道が事後の交渉では一転、認められた筈の因果関係を否定して自殺の賠償には応じられないと主張し始めたため、遺族は裁判を起こさざるを得ない状況に追い込まれた。
函館地裁での審理は初弁論後、非公開の弁論準備期日の形で進められることになり、12月24日には2回目の期日が設けられた。ここであきらかになったのが、被告の道側によるハラスメント全否定の主張。道は先の第三者調査の結果を「必ずしも客観的ではない」とし、同調査で認定された計4件のハラスメントについて、自殺との因果関係以前にそもそも全件ハラスメントとは認められないと主張、調査委の結論をことごとく「適切ではない」と斬り捨てた。認定事案がパワハラと認められない以上、自殺との因果関係も認められないとの理屈で、請求棄却を求めている。
■遺族虐げる鈴木道政
第三者委の認定事案の1つに、被害学生が提出期限に1分遅れたレポートを受け取ってもらえず留年が確定した問題がある。道は今回、これに「1分であろうと提出期限に遅れたことは事実」などとして受け取り拒否を正当化する論を張った。だがこの件ではそもそも「1分遅れた」なる事実が存在しない可能性があり、生前の学生が持っていた携帯電話の時刻では期限に間に合っていたが学校内の時計ではそうではなかったため受理されなかった、との証言があるのだ。
別の認定事案では実習中のハラスメントで死を考えるようになった学生の言動などが同級生らの証言で認められていたが、裁判になった途端、道はこれを「客観的に認定するに足りる証拠はない」とし、いわゆる「言った・言わない」の話に持ち込んだ。そうなると録音データなどの客観的な記録が存在しないケースはすべて認められないことになり、先述した教員11人による53件のハラスメント認定も揺らぎかねない。
遺族側にとって最も不可解なのは、道の担当者が昨年、調査結果を受けて遺族に謝罪している事実。遺族代理人の植松直弁護士(函館弁護士会)は今回の道の主張を受け、改めて「あの謝罪は何だったのか」と憤りを隠さない。
「担当者の謝罪は、知事の謝罪は、いったい何だったのか。そもそも、後になって調査結果を覆すなら、いったい何のために調査委員会を設けたのか……」
植松弁護士が今回の道の主張を原告女性に電話で伝えると、女性は失声して泣き崩れ、大変なショックを受けていたという。遺族側は今後、道が充分に開示していない関係資料などを適切に開示するよう「求釈明申し立て」などを行なう考えだ。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 |