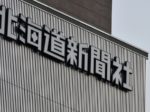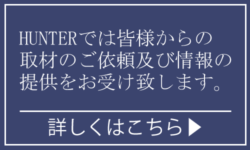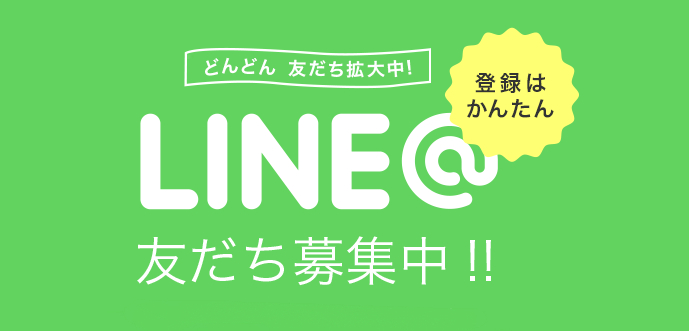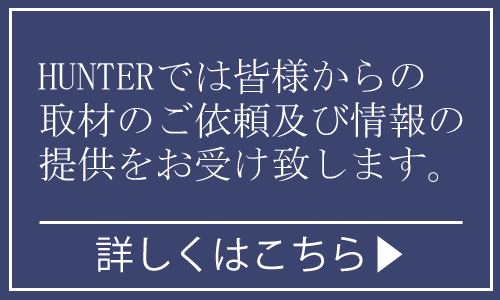ヒグマなどの駆除にあたって市街地や夜間の発砲を認める「緊急銃猟」の要件を定める改正鳥獣保護法の政令案が公表され、パブリックコメントの募集が始まった(⇒コチラ)。政令案では緊急銃猟を担うハンターに過去の狩猟経験や射撃の技術などを問う要件を定めており、北海道のハンターからは駆除従事者に一定の能力を求める動きを評価する声が上がる一方、同時期に非公開で開かれた意見交換会では「ハンターの責任の範囲を明確に」と要望が呈される一幕があった。
◆ ◆ ◆
環境省が意見募集にあたって改正鳥獣法の政令案を公開したのは5月21日。同案ではヒグマ、ツキノワグマ、及びイノシシを「危険鳥獣」に指定し、これらの駆除を目的とした緊急銃猟の担い手には狩猟免許の所持に加えて「過去1年以内に2回以上の射撃」「過去3年以内に危険鳥獣などを捕獲」といった経験を要するとした。また夜間の発砲については「射撃場で50mの距離から5回発砲し、全弾を標的の中心から5cm以内(ライフル銃の場合2.5cm以内)に命中させる」技能を求めた。

こうした要件について「猟師の実績を重視する考え方は評価できる」とするのは、北海道猟友会砂川支部長を務める池上治男さん(76)。本サイトでたびたび報告している銃所持許可取り消し訴訟の一審原告として現在、北海道公安委員会を相手どる裁判で最高裁に上告を申し立てているところだ(既報)。狩猟歴約40年の池上さんは、「ハンターにもバッジテストのようなものが必要」と訴える。
「北海道でも実際にヒグマを撃ったことがあるハンターは、ごく少数。中には、箱罠にかかったクマも満足に撃てない人がいるほどです。いくら法を改正して市街地で撃てるようになったからといって、経験のないハンターに簡単に撃たせてはいけない。地元の砂川では、実際にクマを駆除すると決まった時は必ずショットガン2人・ライフル2人の4人体制で臨場していますよ」
パブリックコメントの公示と前後し、北海道では5月19日から自治体やハンターとの意見交換会が始まった。議論は非公開で進められたが、参加者によると改正法について猟友会から少なからぬ苦言が呈される場面があったという。多くのハンターが意を強くしたのが、猟友会役員による「責任の所在」についての疑問の声。猟友会は飽くまで猟を趣味とする団体で、危険鳥獣の駆除はボランティアの一環で引き受けている。本来、国民の安全を守るのは自治体や警察ではないか――、そんな問題提起にも聴こえる意見だったといい、道内の支部からはさらに具体的に「銃を貸すから警察が撃てばいい」との声も上がったという。
現場のハンターが懸念しているのは、先の銃所持訴訟に発展したケースのように、自治体の依頼でクマを駆除した挙句に銃を取り上げられる事態。行政が法改正で駆除の機会を拡大する一方、司法は駆除に貢献したハンターに罪を着せるような判決を下しており(⇒判決 )、多くの猟友会関係者が責任の所在に不安を抱えているという。当事者の池上さんは「道警は早く誤りを認めてもらいたい」と呼びかける。
「最高裁の対応が決まる前に道警が自ら誤りを認め、銃を返してくれたらそれで終わる話なんです。法改正にあたっては鈴木直道知事が道猟友会の会長に同行して環境省へ申し入れをしていますが、そんなことをするぐらいなら一審で警察の誤りを認めた裁判になぜ知事として控訴したのか…。今回の意見交換会にしても、非公開にする意味がわかりません。万が一、裁判で私の敗訴が確定するようなことになったら、道と猟友会との間に今後ずっと禍根を残すことになりますよ」
池上さん裁判の最高裁の判断は、5月20日時点で伝わっていない。環境省のパブリックコメントは6月20日まで募集中となっている。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 |