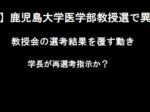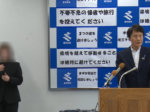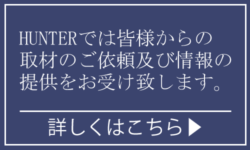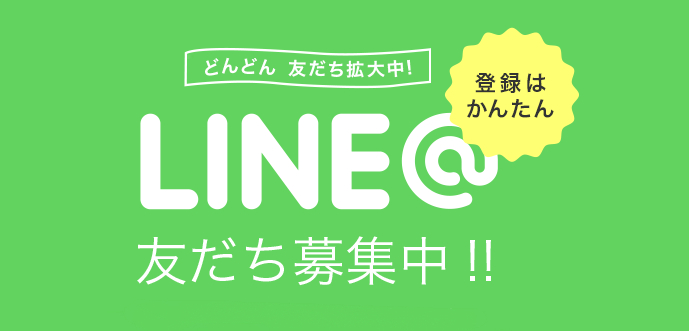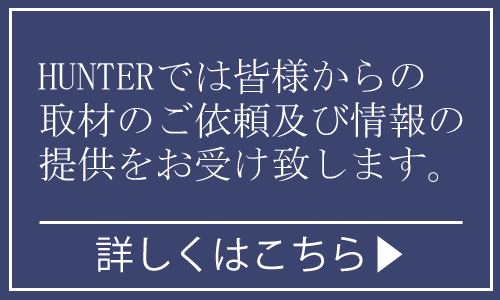【江差看護学院自殺訴訟】加害教員らに“パワハラ”の反省なし|第三者委聴取記録が示す醜い言い訳
北海道立江差高等看護学院のパワーハラスメント問題で、在学生の自殺事案を検証した第三者調査委員会の聴取に応じた教員らが、加害の認識を欠いた主張をしていたことがわかった。亡くなった学生の遺族が北海道を訴えた裁判で、遺族側の求めに応じて道側が証拠提出した聴取記録に、そうした教員らの発言が残されていた。
◆ ◆ ◆
本サイト既報の通り、問題の事案は2019年9月に発生。江差看護学院に在学中だった男子学生(当時22)が教員のハラスメントを苦に自ら命を絶った。遺族の求めで道が設置した第三者調査委員会は教員や卒業生らへの聴き取り調査の結果、学生の自殺とハラスメントとの相当因果関係を認定。調査結果を受けた道は一昨年5月に遺族へ謝罪し、鈴木直道知事も謝罪コメントを出した(⇒)。ところがその後の遺族との賠償交渉では一転、道は先の因果関係を否定し始め、不信感を募らせた遺族が改めて損害賠償を求める裁判を起こしてからは、さらにハラスメントの存在自体を否定する論を張るに及んだ。
その裁判は昨年9月、学生の母親(48)が函館地方裁判所に提起。10月下旬に最初の口頭弁論を迎え、同弁論を含めてこれまでに4回の日程が設けられたが、2回目以降は非公開の弁論準備手続きの形で進められている。7月に予定されている5回目の日程も非公開だが、裁判所ではこれまでの裁判の記録を保管しており、所定の手続きを踏めば誰でも調書や証拠などを閲覧できるルールがある。筆者は第4回の日程終了後の5月下旬、函館地裁で同記録を閲覧し、第三者委の聴取記録が証拠提出されていた事実を確認した。
裁判記録によると、聴取の記録は昨年12月と本年2月の2度にわたり、遺族側の求釈明(説明の要求)に応じて道側が提出していた(乙3~9号証、及び乙10~15号証)。いずれも学生が亡くなった当時の学校関係者や元学生らへの聴き取りの内容を文章化したもので、聴取時期は2022年11月から23年1月まで。多くは札幌や函館のホテル会議室で委員3人が直接面談して質疑応答を行なっていたが、一部の元教員については当事者の希望により電話聴取の形で実施されていた。
記録には、本サイトで逐次伝えてきた元同級生や元職員の証言が詳しく記載されているほか、学生と同じようにハラスメントの被害に遭っていた元教員らの証言も収録されていた。当時の副学院長らのパワハラで4年間にわたって看護教員免許取得の研修に参加させてもらえなかったという元講師は、くだんの学生の自殺が発作的な事故ではなくハラスメントが積み重なった結果だったとの見方を、次のように語っている。死の直前、学生が自身のロッカーを綺麗に片づけていたという逸話に触れた発言だ。
《たぶん家で急に思い立ったということではないと思います。そうすると、片付けているので、その日の朝のことなので、前に考えて、片付けてっていう感じだと思うんですよね》
別の元教員はさらに、ハラスメントの「主犯」と目される女性教員の重大な差別的発言を憶えていた。亡くなった学生の家庭環境をめぐり、次のような暴言が聴かれたという。
《母子家庭だというように、両親(りょうおや)で育ててない人はこうだね、っていうふうに言って、それでお父さんがいない子って、学校にいた時に聞いたことがある》
聴取した委員が「片親だと能力が低いということか」と尋ねると――、
《能力が低いというか、考え方に偏りがあるとかそういうことを言っていたようです》
さらに、亡くなった学生の担任を務めたことがあるという元教員は、当時の異様な職場環境を生々しく証言していた。在職中の7年間に少なくとも6人の教員がパワハラを苦に辞職したこと、元教員自身も2年目に鬱になり「どうやって死のうか」と考えながら毎日トイレで吐いていたこと、学生からお金を巻き上げていた教員が副学院長の胸三寸で行為を黙認されていたこと、それらの記憶が今も残るため恐くて教育の現場に戻れないと思っていること……。
ならばその、学生や同僚教員などへの加害行為を指摘されるハラスメント関与教員らはどういう認識だったか。結論から述べると、いずれもほとんど反省の色が見えず、そもそも自身の行為をハラスメントとは思っていないような主張を展開しているのだった。パワハラの中心にいた元副学院長は、当時の指導のどこに問題があったかと問われた際、悪びれず次のように答えている。
《ハラスメントと認定されていますけれども、言った言わないということもあるので、こちらとしては言った記憶がないことも、言ったっていうふうに言われて、それが認定されたりという人もいますし、あと、学生に対して奮起させようとして言ったことが全部ハラスメントって認定されて奮起させる訳にいかないんだって感じました》
ほかの発言も、推してしるべし。学生の死という最悪の事態にショックを受けるでもなく、遺族への悔やみを述べるでもなく、ただただハラスメント認定を心外そうに否定し続ける。くだんの学生の人となりを語る発言に到っては、あたかも自殺の原因を本人の人格に求めているかのように読み取れるものだった。
そして、かの学生へのハラスメントの「主犯」と目される元教務主査の女性。同元主査のパワハラをめぐっては別の女子学生も被害を訴え「灯油飲んだら死ねるかな」と発言していたという逸話があり、元主査自身もそれを憶えていた。亡くなった男子学生とのかかわりでは、同学生に剣道の竹刀を持たせてグラウンドを走らせていたという証言が複数ある。だがこれは、本人に言わせれば学生自身が任意で始めたことになるようだ。
《運動をしたら気分が晴れたり気分が前向きになるので、運動もしてみたら良いかと思うよっていうことも勧めて。その頃は授業とかもなかったので、学校に来ることとかもあまりなくて、家にずっと閉じこもりきりで、何も自分で楽しめるようなことがないと言ったので、何かしてはどうかという話をして》
《だったら、私は今剣道とかもやっていたので、そこで、やると気が紛れたりとか気分転換にもなったりするという話もして》
《一方的に走ってみたらどうかとか、言ったわけではなくて、そこは、結構な話し合いの中で、■■君がやってみたいなって言ってくれたことだと思って、それで始めました》
語り手の必死さだけは伝わるが、およそ説得力には乏しい。“死人に口なし”と思っているのだろうが、身も蓋もない言い方をするなら、何を言おうとしているのかわからない。
学生などパワハラ被害者たちと加害教員たちとの主張の喰い違いは、ほかにもある。亡くなった学生のレポート提出が締め切りに間に合わず受理してもらえなかったという話題で、元同級生らは教員室の時計が数分間進んでいただけで実際は締め切りに間に合っていたと証言する。これに対し、パワハラ関与教員らは異口同音に時計は正確だったと断言。ただその根拠は曖昧で、話者によって時刻の基準が「授業のチャイム」「電子時計」「中央の時計」などとブレている。第三者委に一部記憶違いを指摘された元教員でさえも「時計は正確だった」という一事についてはなぜか自信に満ちた口調で言い切っているのだ。
こうした発言の数々は、繰り返しになるが裁判所を訪ねて所定の手続きを踏めば誰でも確認することができる。実際、筆者が記録を閲覧した時点でこれまで計28件の閲覧申請があり、閲覧者が実人数で10人いたことが確認できた。10人のうち9人は報道関係者で、一部はその成果をニュースとして報じている。憲法で認められている裁判の公開原則に照らして至極真っ当な取材活動といえるが、滑稽なのは被告の道側がこうした情報発信に臆面もなく苦言を呈している点。道側は準備書面で、裁判で示された事実が報道機関から発信されると原告代理人への不信が募るなどと主張しているのだ。
結びに、この道の姿勢について国民の1人として疑問を述べておく。自治体としての北海道は、先進国らしからぬ秘密裁判をお望みなのか――。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 |