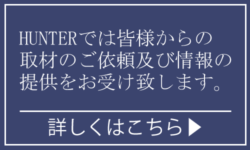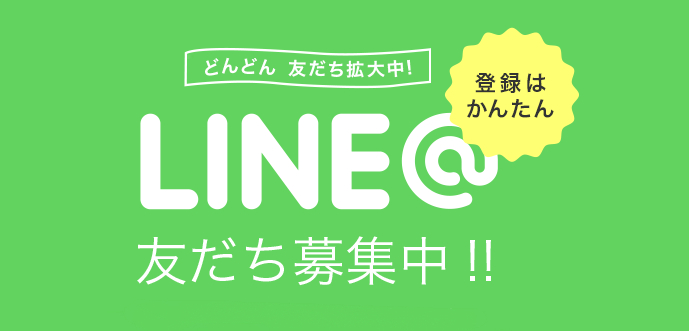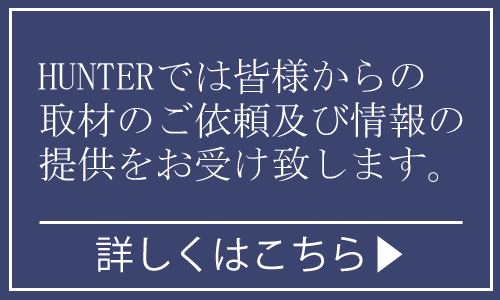令和の米騒動の報道が冴えない。冴えなくて当たり前なのかもしれない。主要メディアには「農林水産業を専門に取材する記者」は、今やほとんどいない。日頃きちんと取材していないから、急に米価が高騰し、政府備蓄米の売却が決まっても、「コメの流通って、そもそもどうなってるの」という初歩から取材を始めるしかないからだろう。
「コメの値段がこんなに上がっています」と現状を伝え、「備蓄米を放出したのに店頭に出てきません。値段はまだ上がっています」と、事態の推移をただ伝えるだけ。小泉進次郎氏が農水相になり、備蓄米を随意契約で売却した結果、すみやかにスーパーの店頭に並ぶと、それをパパラッチのように追いかけて映像を流す。毎日、そんな報道ばかりだ。
戦後の食糧管理制度の変遷と、その中で農業協同組合(JA)と農水省が果たしてきた役割を深く知る者なら、今回の米価高騰の元凶は「JAと農水省である」とズバリ指摘し、その核心にギリギリと迫っていくことができるのではないか。
私は農業問題の専門記者ではなかった。「深く知る者」とはとても言えないが、それでも「元凶はJAと農水省」という核心にたどり着くための手がかりくらいは示すことができる。
今回の米価高騰の発端は、昨年8月8日に気象庁が南海トラフ地震の臨時情報(巨大地震注意)を発表したことである。なにせ、被害想定は死者約30万人という大地震だ。それが差し迫っているかのような発表があったのだから、人々があわてふためいたのは当然だろう。
大地震に備えて、多くの人が食料の買いだめに走った。コメを置いているスーパーの棚はほどなく空っぽになった。その後、お盆前後に台風が相次いで襲来し、米作農家が打撃を受けた。「コメの需給が逼迫するのではないか」との観測が強まり、米価の高騰に拍車がかかった。
下のグラフは、2024年(令和6年)産米の相対(あいたい)取引の平均価格がどのように上がっていったかを示したものだ。コメの相対取引とは、JAなどの集荷業者が卸売業者に販売する取引で、玄米60キロ当たりの取引の平均価格を示している。棒グラフは月ごとの取引量である。

2023年(令和5年)産米の9月の相対取引価格は、平均で1万5,291円だった。それがグラフに見るように、2024年9月には2万2,700円と1.5倍になり、今年の4月には2万7,102円とさらに高騰した。JAが卸売業者に販売したコメは二次卸、三次卸を経て小売店に並ぶ。その都度、マージンと流通経費が上乗せされ、小売に並ぶ段階では2倍の値段になってしまったのである。
次のグラフは、2012年(平成24年)産米から2024年(令和6年)産米の相対取引価格の推移を示している。これを見れば、2023年(令和5年)産米までは玄米60キロ当たり1万2,000円から1万6,000円前後で推移しており、年間を通して安定していたことが分かる。2024年産米だけが9月以降、異様な形で高騰したことがよりハッキリと見て取れる。

JAが収穫時期に農家から買い取る際の仕入れ価格は概算金と呼ばれ、米価が上がれば農家に追加金が支払われるが、それでも米作農家の手取りは2倍にはなっていない。スーパーを含めた小売り段階では競争が激しく、そのマージンは限られている。小売り段階で値段が跳ね上がることは考えられない。要するに、JAをはじめとする集荷業者と大手の卸売業者が「高値相場」を作り出し、しこたま利ザヤを稼いでいるのである。
政府が備蓄米を売却してこの高値が崩れたりしたら、JAも卸売業者も困る。そこで、江藤拓・前農水相は「備蓄米を買った業者は1年以内に同じ量を政府に戻さなければならない」という条件を付けて入札にかけた。こんな条件を付けたら、応札できるのはJAくらいしかない。
かつての食糧管理制度の下では、JAがほぼすべてのコメを集荷し、卸売業者に販売していた。食管制度が廃止になり、コメの流通は自由化されたが、それでもJAは今でもコメの全流通量の4割を扱っており、最大の集荷業者である。競争入札なら備蓄米を高値で落札して独占し、市場に流すのも遅らせれば、高値を維持できる。そうやって利ザヤを稼ぎ続けるつもりだったのだろう。農水省の官僚たちも「それで構わない」と考えたはずだ。なにせ、トップの大臣が「(コメを)買ったことがありません。支援者の方がたくさん下さるので」と平気で言う人物なのだから。
そこに、JAや農水省の思惑など気にしない小泉進次郎氏が登場し、「備蓄米を随意契約で売る」「コメが5キロ2000円で売られるようにする」と宣言し、実現してしまった。JAも農水省も心穏やかではいられない。今の高値が崩れれば、JAも卸売業者も大損する恐れがあるからだ。そうなると頼れるのは、自民党の農水族しかない。
さっそく、野村哲郎・元農水相が「(随意契約による備蓄米の売却は)自民党の了承を得ていない。ルールを覚えていただかなきゃいかん」と小泉氏に苦言を呈した。農水省出身の鈴木憲和・復興副大臣は「国がやるべきことは備蓄米の放出ではない。すべての国民に平等に行き渡るようにすることだ」と、トンチンカンな発言で随意契約による売却に異を唱えた。
普通の市民にとって、主食のコメが倍の値段になるということは大変なことだ。とりわけ、所得の低い人ほど打撃が大きい。こういう発言をする政治家はその切なさがまるで分かっていない。自分の支持母体であるJAとこれを支える農水省のことしか頭にないようだ。
その農水省の幹部も、コメを作っている農民のことやこれを食べる人たちのことなど気にしていない。農水省の本川一善・事務次官はJA全農の経営管理委員に天下った(2017年)。荒川隆・官房長も2020年にその後任として同じポストに就いた。「退職後にお世話になるところに不利なことなどできません」というのが本音だろう。
日本の農業の未来を見据え、この国の食糧安全保障に心を砕く官僚は農水省には一人もいないのか。
長岡 昇:NPO「ブナの森」代表
長岡 昇(ながおか のぼる)
山形県の地域おこしNPO「ブナの森」代表。市民オンブズマン山形県会議会員。朝日新聞記者として30年余り、主にアジアを取材した。2009年に早期退職して山形に帰郷、民間人校長として働く。2013年から3年間、山形大学プロジェクト教授。1953年生まれ、山形県朝日町在住。
≪注≫グラフ1、2はいずれも農水省のサイトから抜粋 ⇒こちら
≪参考サイト≫
◎『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し(三菱総合研究所、稲垣公雄) ⇒こちら
◎『令和のコメ騒動』(2)コメ価格の一般的な決まり方(同) ⇒こちら
◎農林水産省における天下りの実態調査報告 ⇒こちら