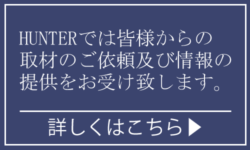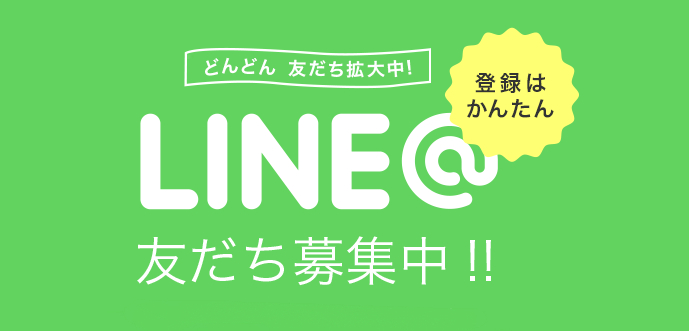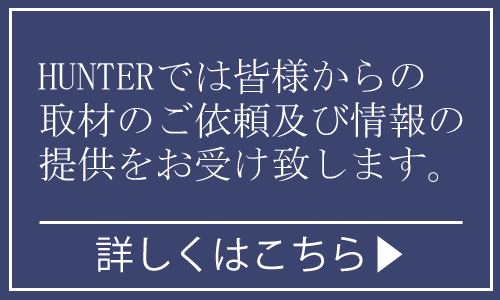刑事事件の容疑者取り調べへの弁護人立ち会いについて、北海道警察がこれを認めないとする内部通達を出していた問題で、地元報道や弁護士会などの批判を受けた道警が8月に入って同通達を作り直していたことがわかった。問題とされた通達について、中央の警察庁は「誤解を招きかねない表現があった」としている。
◇ ◇ ◇
本サイト既報の通り、同問題をめぐっては昨年12月、札幌弁護士会が道警に申し入れを寄せ、刑事事件の取り調べに弁護人の同席を認めるよう求めていた。これを受けた道警は申し入れ直後に刑事部長名の通達を出し、弁護人から立ち会いの求めがあっても一切認めないよう各警察署などに指示したことがわかっている。
弁護人の取り調べ立ち会い権を明文化したルールはないものの、さりとて立ち会いを明確に禁じる法律があるわけではなく、国家公安委員会の「犯罪捜査規範」には第三者の取り調べ同席を想定した条文がある(180条2項)。実際にはほとんどのケースで同席が認められていないとはいえ、立ち会う権利そのものは決して否定されておらず、全国の都道府県警察を監督する警察庁も昨年5月、各警察本部などに宛てた事務連絡に次のような考えを記していた。
《弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要がある》
《弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい》
立ち会いを一律に否定する道警通達は、これらの原則に適っているとはいえなかった。地元紙・北海道新聞は本年7月から8月にかけ、紙面でこの喰い違いを指摘。同紙の報道を受けた札幌弁護士会が改めて道警に抗議を寄せる事態となり、さらには札幌のみならず道南の函館弁護士会も会長声明を発表( https://hakoben.or.jp/archives/statement/1309 )、道警通達を強く批判して撤回を迫った。
こうした動きを受けた道警が問題の通達を見直し、新たな通達を出していたことがわかったのは、8月下旬のこと。現在、公文書開示請求中の筆者はその内容を確認できていないが、先んじて同通達を入手したとみられる道新や朝日新聞の報道によると、新たな通達は8月18日付で発出。もとの通達の「立会いは認めないこと」などの文言は削除され、組織的に判断するとの内容に変更されたという。事実上、弁護士会などの抗議を受けて昨年の通達を撤回した形だが、この真意などを尋ねる筆者の取材に道警は現時点で回答を返していない。一方、8月下旬に取材を打診していた警察庁は同30日午前の文書回答で次のような認識を示すに到っている。
《北海道警察が発出したお尋ねの通達については、一部に誤解を招きかねない表現が認められたことから、誤解が生じないよう表現を改めた通達を発出し直したと報告を受けています》
取り調べへの弁護士同席を「認めない」と明記した通達の文言は「誤解を招きかねない表現」だったというのだ。この説明が腑に落ちるものになっているかどうかは、読者の公平な評価に任せたい。
なお札幌弁護士会は昨年12月の道警への申し入れに際し、もう1つの捜査機関である検察にも同じ趣旨の求めを寄せている。今回の道警の問題を受け、筆者が札幌地方検察庁の定例会見で立ち会いの可否などを判断するルールについて尋ねたところ、同地検の次席検事は「(ルールの有無を)把握していない」と回答、過去に立ち会いを認めたケースがあるかどうかを確認する問いには「私が承知している範囲では、ない」と答えている。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 |