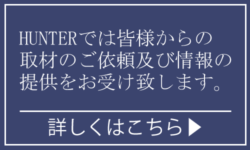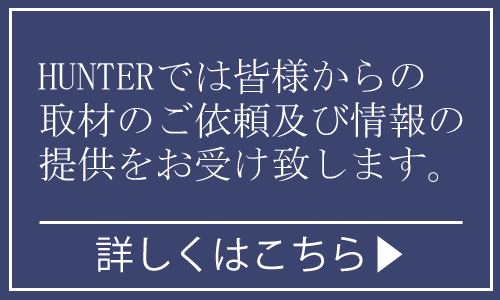地元住民の反対を無視して、鹿児島県が鹿児島市松陽台町で建設を強行した「県営松陽台第二団地」。約10年かけ328戸を整備する計画だったが、何度か入居条件や建設戸数が変更となり、最終的には280戸を造る予定となっている。
計画変更を余儀なくされてきた理由は、同団地の不人気。ハンターは、2011年からこの問題を追及してきたが、事業が完結する前に関係者の“懸念”が現実味を帯びる状況となっている。
■苦し紛れの「子育て支援住宅」
松陽台の県営住宅建設計画は、2003年から鹿児島県住宅供給公社が販売してきた分譲住宅地「ガーデンヒルズ松陽台」の土地を鹿児島県が約30億円で取得し、新たに「県営松陽台第二団地」328戸を建設するというものだった。
もともと住宅供給公社の計画では、約11haの予定地に戸建用地470区画を販売する計画だったが、170区画程度(2011年2月までの実績)を販売したしたところで売れ行き不振が深刻なものとなり完売を断念。県は、ガーデンヒルズ松陽台で最大の面積を占める戸建用区画約5.6haを、すべて「県営住宅」にすると発表する。公社の失敗を税金で穴埋めするという県の身勝手な方針転換だった。
これに対し、周辺環境が激変することなどを憂慮した松陽台町の戸建て住宅に住む住民は、県営住宅建設を白紙に戻すよう反対運動を展開。しかし、走り出したら止まらないのが公共事業の常で、県や鹿児島市はこうした声を無視して強引に計画を進め、2014年春から建設工事を進めてきた。
だが、無理な計画には落とし穴がつきもの。強引に住宅建設計画を進めたものの、アンケートによって、古くなった市内の県営住宅から住み替えを希望する県民がほとんどいないことが判明。県は松陽台第二団地への入居者を、低所得の子育て世代――しかも就学前児童のいる家庭に限定するとして、「子育て支援住宅」にする方針を打ち出す。苦し紛れの弥縫策だった。
入居期間は原則10年。しかし、小学校にあがるまでに6年、さらに小学校で6年、これだけで「12年」になるため辻褄の合わない計画だ。県は入居期限の延長制度を設けるとしていたが、≪小学校を卒業するまで入居可能な制度≫(県のホームページより)に批判は絶えなかった。“子どもが中学生になったら、出ていけ”という、無責任な子育て支援だったと言わざるを得ない。
だが、せっかくできた新築の子育て支援住宅は、初期の募集にこそ注目が集まったものの、その後の人気は尻すぼみ。いまでは、不人気団地の一つに数えられるようになっているという。
不人気の理由は、「不便」ということに尽きる。鹿児島市内の中心地に位置する鹿児島中央駅から松陽台町があるJR鹿児島線上伊集院駅までは二駅、約10分。車だと30分以上かかる。保育所・幼稚園も小・中学校も整備されていない上、商業施設もない。小学生は、「鹿児島市立松元小学校」に通うため、地元の上伊集院駅から一つ先の薩摩松元駅まで“電車通学”を強いられているのが実情だ。
松陽台第二団地は「子育て支援住宅」のはずだが、子育て環境は最低。15年10月には「薩摩松元駅」で小学生のホーム転落事故が、2018年1月には町内にある「松陽台ふれあい公園」で女子高生が刃物で殺傷されるという事件も起きている。
「近くに小学校や幼稚園・保育園がない」、「何をするにも車が必要で、買い物が大変」、「危険な場所が多く、子供だけで遊ばせられない」――松陽台の県営住宅内を歩けば、必ずと言っていいほど、こうした声が返ってくる。1年、2年と住むうちに、「やっぱり、市街地に近い方がいい」と引っ越す人は少なくないという。それでも進められてきた『言葉だけの子育て支援』(地元住民)を掲げた県営住宅増設事業……。県政を刷新すると叫んで2016年に知事になった三反園訓氏は、何の手も打たず黙殺。県政にとっては三反園時代の空白の4年間が、松陽台第二団地を巡る“被害”を拡大させた。
■入居条件、次々変更
不人気の理由の一つにもなっていた子育て支援住宅の「入居条件」が、2020年になって変更される。
前述したように、県営松陽台第二団地は子育て世帯向け団地として、入居から10年間の期限つきで入居できる団地。入居期限は《子供が小学校を卒業するまで》だった。しかし20年、これを《末子が中学校を卒業するまで》と延長。さらに県は、今年4月から《末子が18才に達するまで(高校を卒業するまで》と再改定している。(*下が県のホームページにある入居制限延長の告知)
募集対象も変更になった。県は「中学校就学前の子供を持つ世帯」としてきた募集対象に、「既存の一般世帯向け公営住宅に住む子育て世代」を加えたのだ。転勤などのやむを得ない理由がない限り、県営住宅から県営住宅への転居は認められていないのだが、特例として松陽台第二団地への入居だけは許すということだ。(*下が県HPの告知)
 一体なぜ県は入居のハードルを下げ続けなければならないのか――。ハンターの記者は昨年秋から何度か現地に足を運び、その理由を確かめた。
一体なぜ県は入居のハードルを下げ続けなければならないのか――。ハンターの記者は昨年秋から何度か現地に足を運び、その理由を確かめた。
(以下、次稿)




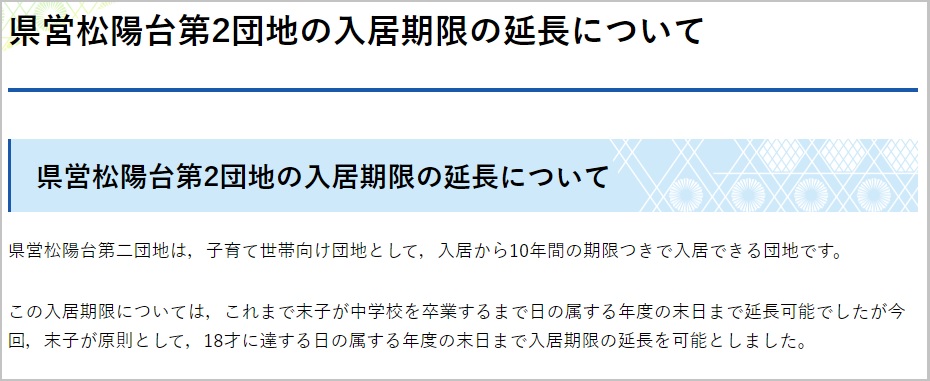






-150x112.jpg)