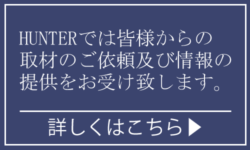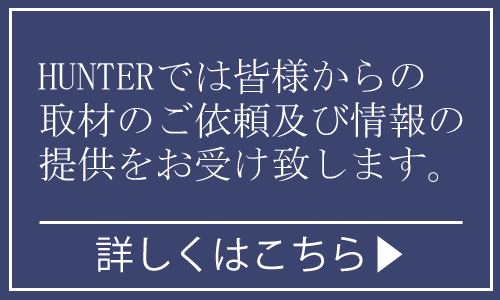「人間を人間として見て欲しい。同じ人間に、どうして手術までして子供を産むなって言えるのか」――札幌市の小島喜久夫さん(79)が、憤りの声を法廷に響かせる。旧優生保護法下で不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判が各地で続く中、全国で初めて顔と名前を晒して名乗りを挙げた原告が6月19日、札幌地裁で尋問に立った。
■理不尽な強制手術、全国で1万6,475件 無理やり手術室に入れられ……
原告の小島さんは、札幌に隣接する石狩町(現・石狩市)出身。子供のいなかった農家に養子として引き取られ、のちに同家夫婦に実子が産まれたため、幼いころから育児放棄を受けるようになったという。中学生のころから非行に走り始め、遊ぶ金を両親に無心しては不良仲間とつるんで悪さを続けた。
19歳になったばかりのある日、実家に小遣いをせびりに行くと、そこに交番の警察官が待ち受けていた。いきなり手錠をかけられ、バイクの後部座席に乗せられる。驚いて抵抗すると、養親は「お前のような素行の悪い奴は一生閉じ込める」と言い捨てた。最寄りの警察署へ向かうかと思われたバイクは、札幌市の精神科病院へ。出迎えた看護婦(当時)は、診察もなく宣告した。「あんたは精神分裂病(統合失調症)だから、優生手術を受けることになる」――。
戦後まもない1948年に生まれた旧優生保護法。「優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止する」(同法前文)ことを目的に、障害のある人や特定の病気に罹患した人などに不妊手術をすることを認めた法律だ。手術は任意とされていたが、国が定める疾患56種のいずれかが認められた人については、都道府県の審査で「強制手術」を行なえることになっていた。19歳の小島さんが受けることになった手術が、それにあたる。

不妊手術は、この旧法が1996年に母体保護法と名を変えるまでの48年間にわたって続いた。約半世紀で報告された全国の執刀数は計84万4,968件。このうち強制手術は1万6,475件に上っている。都道府県別で最も多い数字を記録したのが北海道で、総数の6分の1以上を占める2,593件が記録に残る。1,000件を突破した1965年には、道が『優生手術(強制)千件突破を顧みて』なる記念誌を作ってその実績を振り返っていた。
国を挙げて、障害のある人たちの断種をよしとしていた時代。裁判を起こした小島さんに到っては、障害の診断なしに手術を強制されていた。法そのものが人権を侵していただけでなく、法の要件を満たさない強制手術さえもが横行していたのだ。
「私のほかにも、病気や障害がないのに閉じ込められた人たちがいました。頭にロボトミー手術(非人道的な精神外科手術)の痕がある人も見た。手術の順番が回ってくると、注射を打たれ、無理やり手術室に入れられ、ベッドに縛りつけられて……」
当時の生々しい経験を法廷で明かした小島さん。国の責任を追及する語りでは、込み上げる感情を抑えきれず涙を流す一幕もあった。
「手術は病院の判断だと、ずっと思っていました。しかし、本当の責任は国にあることがわかりました。国が、悪いことをしたんです」
30歳代で結婚した妻の麗子さん(76)には、長いこと手術の経験を隠していた。子供がつくれない理由を問われ、「小さい時、おたふく風邪をやったからじゃないか」とごまかすしかなかった日々。誰にも言えない秘密は、墓場まで持っていくつもりだった。2018年1月までは――。
そのころ、宮城県の女性が優生手術の被害を明かし、国を訴えたというニュースに接した。それを機に、各地の弁護士が全国に被害相談窓口を設けたという。いても経ってもいられなくなり、意を決して麗子さんに打ち明けた。「おれもあの手術、受けたんだ」。事実を知った麗子さんは、驚きつつも相談窓口への連絡を促し、国との闘いを意識し始めた夫の背中を押す。同年5月17日、国を相手に1,100万円の損害賠償を求める訴訟を提起。先立つ4月には実名で新聞記者の取材に応じ、全国で初めて顔と名前を晒して被害を告発した。

当時の筆者の取材に、小島さんはこう答えている。
「名前を出したのはさ、同じ被害に遭った人たちにも勇気を出して立ち上がって欲しいと思ったから。おれはその後、病院を抜け出すことができたけど、一緒に閉じ込められてた人たちの中には、何年も出られなかった人もいるかもしれない。そういう人たちに、おれの顔を見て思い出して欲しいのさ、自分も国にひどい目に遭わされたんだ、って」
思いが通じたのか、北海道ではさらに2人が原告に加わり、道外でも実名を公表する被害者が増えた。先立つ仙台訴訟を含め、裁判の提起は各地で1つまた1つと増え続け、これを受けた国は小島さん提訴翌年の19年4月、被害者への一時金支給法を成立させる。だがその条文には、国の責任を認める言葉が一切盛り込まれず、謝罪もなされなかった。これが原告らの怒りに火を注ぎ、裁判はその後も闘われ続けることになる。
■半年ぶりの法廷で……
小島さんの裁判では今年3月に8回目の口頭弁論が設けられる予定だったが、感染症の影響でこれが非公開の弁論準備手続きとなり、6月の尋問は半年ぶりの法廷となった。被害を訴える小島さんに対し、被告の国は訴訟の取り下げを求め続けている。根拠としているのは、「除斥期間」。刑事事件でいう時効に相当する考え方で、被害の発生から20年以上が経過していることを盾に、被害回復の義務がなくなったとする主張だ。
今回の尋問では、札幌地裁の廣瀬孝裁判長自らがこの除斥期間に言及、原告代理人らが裁判長と小島さんとのやり取りに神経を集中させて聞き入ることになる。
裁判長「この訴訟では、除斥期間の適用の有無が問題となっています。わかりやすく言うと、『訴えを起こすのが遅すぎたのではないか』と。そこでお伺いするのですが、この訴訟を起こしたのが平成30年、なぜこの時まで訴えを起こさなかったのですか」
小島さん「国がやったんだっていうことは、全然知らなかったんです。新聞でも読んだことないし、仙台の人のことをニュースで知るまでは、病院がやったとしか思ってなかったんです」
仙台の訴訟では一審で原告の訴えが棄却され、現在は控訴審の弁論が続いている。小島さんの裁判は次回、9月25日に結審し、年明けにも判決に到る見込みという。札幌の訴訟代理人らは、憲法判断に踏み込んだ判決に期待しているところだ。
尋問後の報告集会で、手術の被害を隠し続けた57年間を振り返った小島さんは、改めて裁判に賭ける思いを語っている。
「うちのやつ(妻・麗子さん)の理解があったから、ここまで来られた。これからもうひと頑張りして、勝たなければならないと思っています。私は自分を不幸な人間だと思ってきましたが、これからはそうではないと思える人生にしたい」(下の写真)
 優生保護法下の強制不妊手術の被害を訴える裁判は現在、全国8カ所で係争中(札幌、仙台、東京、静岡、大阪、神戸、福岡、熊本)。これまでに24人が原告に名乗りを挙げ、うち6人が実名を明かして闘い続けている。
優生保護法下の強制不妊手術の被害を訴える裁判は現在、全国8カ所で係争中(札幌、仙台、東京、静岡、大阪、神戸、福岡、熊本)。これまでに24人が原告に名乗りを挙げ、うち6人が実名を明かして闘い続けている。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 北方ジャーナル→こちらから |



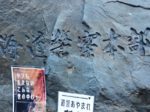






-150x112.jpg)