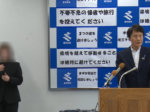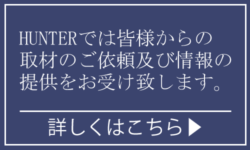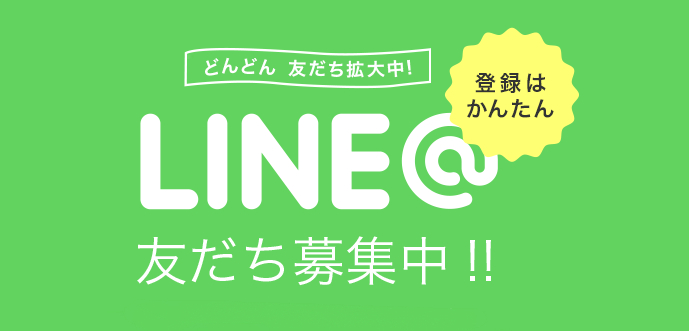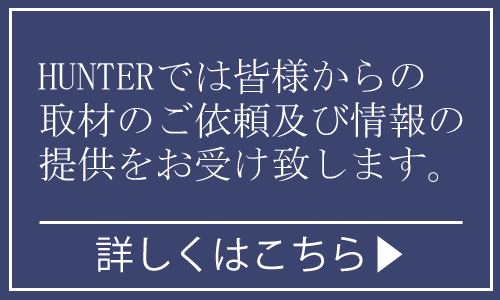審査会答申は→こちら(PDFファイル)
警察の「闇」に光が当たる可能性が出てきた。鹿児島県警察が職員の不祥事に係る事件捜査記録の開示を拒んでいた問題で(既報1)( 既報2 )、筆者の審査請求(不服申し立て)を受けた第三者機関が10月中旬までに県警の当初決定を不当とする答申をまとめていたことがわかった。県警は同答申に基づき、改めて当該文書の開示・不開示の決定をやり直すことになる可能性が高い。
◆ ◆ ◆
筆者が鹿児島県警に開示を求めていたのは、同県警で処分などがあった不祥事(懲戒処分・監督上の措置)のうち法令違反として捜査の対象になっていた事案の捜査記録など。県外の警察機関(北海道警など)では同旨の請求に応じて「事件指揮簿」や「犯罪事件処理簿」などの公文書を一部開示しており、鹿児島でも同様の対応が期待されたが、昨年3月の請求に対して同5月に伝えられた結論は、存否応答拒否。即ち、文書が存在するかどうかを明かさずに対応を拒むという決定だった。
これを不服とした筆者は同7月、同決定が不当な隠蔽にあたるとして審査請求を申し立てた。県警が存否応答拒否の根拠に挙げたのは、県情報公開条例7条1号(個人に関する情報)と同4号(公共の安全等に関する情報)。当該文書の存否を明かすことが個人情報や公安情報の侵害にあたるとの理屈だが、すでに述べたように鹿児島以外の道県警では同旨の請求に対応して当該情報を開示することができている。筆者は北海道や福岡県のケースを例示して鹿児島県警の決定の不当性を指摘、もとの決定の取り消しを求めた。
審査請求を受理した県公安委員会(増田吉彦委員長=当時)は8月9日付で第三者機関の県情報公開・個人情報保護審査会(野田健太郎会長・委員5人)へ諮問(意見伺い)、これを受けた審査委は同10月までに県警と筆者、双方の主張を受理し、本年1月から審議に入った。ほどなく結論がまとまるかに思われた議論は4回連続で継続審議となり、この間に同県警によるHUNTER編集部への不当捜査や野川明輝本部長の不祥事隠蔽疑いなどが相継いで発覚、さらに本サイトが昨年11月に報じていた事件記録廃棄指示問題( 既報3 )を報道大手が改めて採り上げるなど、鹿児島県警への批判の声が高まり始めたところだった。
審査委の議論がようやく結論に到ったのは、5回目の審議となった本年9月27日付の審査会。同日に決定した答申は10月17日付で文書にまとめられ、同22日までに筆者と県警の双方に通知された。答申の冒頭、「審査会の結論」として綴られた一文を以下に引く。
《鹿児島県警本部長(以下「実施期間」という。)が、本件審査請求の内容に係る公文書について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、これを取り消し、改めて開示・不開示の決定を行うべきである》
民事裁判ならば「原告全面勝訴」ともいえる決定。審査委は県警側の主張の多くを退け、請求対象の情報は個人情報にも公安情報にもあたらないと判断、当初の存否応答拒否決定は取り消されるべきとの結論を出した。当然といえば当然の決定だが、ここに到るまでに1年以上、当初の開示請求からは1年5カ月ほどの時間が費やされたことになる。とはいえ鹿児島県の審査請求で今回のような「全面勝訴」結果が出るのは珍しく、昨年度の1年間では5件の答申があった中で、請求人の勝率はゼロ。5件すべて県側の決定を「妥当」とする内容、即ち「全面敗訴」の結果に終わっていた。
審査会答申は飽くまで諮問に対する意見表明であり、絶対的な拘束力は持たないが、鹿児島県警がこれを無視して当初の応答拒否決定を貫くのは現実的に難しい。県警の担当課は筆者の問い合わせに「すぐに組織的に報告し、取り急ぎ対応を検討したい」としており、遠からず今回の答申に基づいた決定のやり直しが決まる可能性が高い。
当該文書の開示を求めた目的は、法令違反にあたる警察不祥事を身内の県警が適切に捜査していたかどうかを検証することにあった。文書が開示されれば各事案への対応の適正性が一定程度あきらかになるところ、今後の県警の開示・不開示決定の行方が注目される。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 |