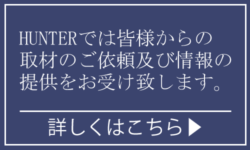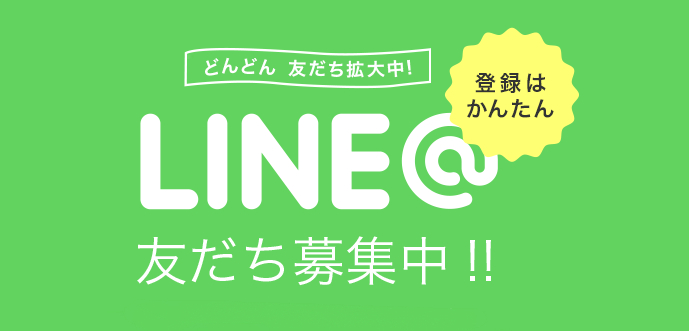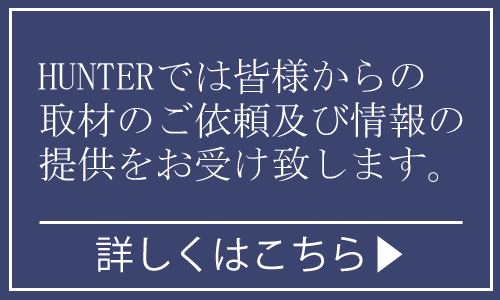北海道立江差高等看護学院の教員によるパワーハラスメント問題で、第三者調査委員会のハラスメント認定報告から一夜明けた13日朝、学院トップが取材に応じ「学生さんや保護者の皆さんにはご迷惑をおかけした。お詫び申し上げます」と謝罪のコメントを述べた。第三者委が認定した52件のハラスメントについては「事実だと思う」との認識を示した。
◇ ◇ ◇
学院前で筆者の取材に応じたのは、一昨年4月に着任した伊東則彦学院長(61)=江差保健所長兼務。一連のハラスメントの「主犯」と疑われる副学院長とは前任地の紋別看護学院でも職場を同じくしているが、実際のハラスメント行為をまのあたりにする機会はこれまで一度もなかったといい、「私がいる場では(パワハラを)控えるようにしていたのでは」と推し量る。
「兼務する保健所長の仕事が業務の8〜9割ほどを占めていて、学院に顔を出せるのは週3回ほど。そこでハラスメントを目にする機会はなく、さらに実習など学院外での出来事となると、知るすべがありませんでした。初めてパワハラを疑うことになったのは今年の3月ごろで、のちに休学する学生さんが大量の『始末書』を書かされていたことを知ったのがきっかけです。結果としてそれまで長いこと事態を看過していたことになり、学院長として監督責任を果たせていなかった。異動や処分などがあれば受け入れる考えです」
学院内では毎月1回、教員らの参加する運営会議が開かれていた。そこには伊東学院長も出席していたが、会議の場で学院長の意見が通るのは「10回に1回ぐらい」で、招集時点ですでに結論が決まっているような空気だったという。「先生たちが私の意見に賛同すると、後から(副学院長らに)いじめを受けることになったのではないか」と、同学院長は推察する。
伊東学院長によると、各地の道立看護学院で「副学院長」のポストが生まれたのは前知事・高橋はるみ氏時代。「女性登用」の一環で同職が新設されたといい、「当初は組合からかなり反対が出たと聞いている」と学院長は振り返る。この「副学院長」が事実上、教学現場の全権を掌握することになった結果、パワハラなどの不祥事が表面化しにくくなり、ひいては問題の長期化を招いた経緯がある。こうした構造的な問題について、伊東学院長は「(パワハラ長期化の原因として)半分はそれがあると思う」と話す。第三者調査委員会もこれを深刻視しており、副学院長と同レベルの職員を各現場に配置するよう道に提言する考えを明かしている。
その第三者委が12日夕に報告したハラスメント認定について、伊東学院長は「(報告の通りの)事実があったと思う」との認識。パワハラ問題を最も早く伝えた本サイトの一連の報道にも触れ、「ハンターの記事は拝見しており、(記事の内容は)その通りだと思う」と述べている。
一連のハラスメントを認定した第三者委は来週までに正式な報告書を道に提出する予定で、これを受けて道の各課が教員の処分や学生の救済策などを決めることになる。江差の学院では先んじてこの10月に教員を1人、新たに採用しており、仮に多くのパワハラ関与教員の処分や異動が決まったとしても、ほかの道立看護学院の教員の一時的な出張などで授業への対応は可能という。伊東学院長は「学生さんにとっては、何をおいても無事に看護師資格を得られることが大事です。今回の件はたいへん申しわけありませんでしたが、どうかこれで動揺することなく、引き続き看護師を目指して頑張っていただきたい」と呼びかけている。
(小笠原淳)
| 【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】 ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。 |